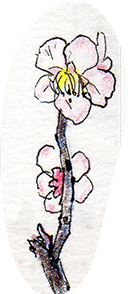「リアル」の糸口
村に越せば万事オッケー、とは決して思いません。思いませんが、都市での生活がぼくにとっては「ヴァーチャル」なものであり、現在の村での暮らしによって、少しずつ「リアル」の糸口が掴めてきているのも確かです。
ぼくは埼玉県の浦和市という(現在はさいたま市ですが)、いわゆるベッドタウンで二十歳そこそこまで過ごしました。小さいころ覚えているのが、砂利道が舗装されアスファルトとなり、どぶ川が埋められて開通した大きな通りに車がビュンビュン走るようになったこと。80年代の終わりから、90年代始めのころの話です。
もちろんその経験が「リアルの喪失」と直接結びつく、といった簡単な話ではありません。そもそもボーイスカウトやキャンプといった「自然体験」が苦手なぼくです。祖父母も都市に住んでおり、田園風景の広がる「田舎」で夏休みを過ごすといったことも全くありませんでした。むしろそのような自然は大嫌いでした。
そんなぼくが、都市に「リアル」を感じなくなったのはいつだったのでしょうか。合気道を習ったり病気をしたり、いつのまにかじわじわと「都市に住めないからだ」になったことが大きいのかもしれません。でもそれが直接の要因だとは思えません。では「リアル」とはなにか。
前述のとおり、ぼくにとっての「リアル」は、村に住むことそれ自体ではありません。そうではなくて、たぶん目の前の「見たくない現実」こそがぼくにとっての「リアル」だったのではないでしょうか。では村は「見たくない現実」を体現しているのでしょうか。いや、これまたそうではありません。もちろん村にもそのような部分はありますが、大事なことは村に住むことによって、「都市から距離をおく」ことだったのです。いつの頃からか都市は、ぼくにとって「見たくない現実を覆い隠すシステム」になってしまったのだと思います。ぼくはそれを「ヴァーチャル」と呼んでいます。
では悲惨で貧しい人びとこそが「リアル」なのかといったら、これまた決してそんなことはありません。貧富を問わずどんな人にも「リアル」は存在するし、貴賎を問わず人はそれを覆い隠しながら必死に生きています。だから「ヴァーチャル」が悪いというわけではない。「リアル」と「ヴァーチャル」を好きな時に行ったり来たりできること。そこにこそ、ぼくは「自由」を感じています。でも「ヴァーチャルリアリティがビジネスになる!」と大手を振って言い歩く人のことを、ちゃんとした大人だとも思えませんけれど。
さて、今年の土着人類学研究会のテーマは「とりあえず、10年先を考える」です。なぜ10年先を考えるのか。もちろん現状を分析し10年間の戦略を立て、敵に出し抜かれないために武器と仲間を集めるため、ではありません。そうではなくて、自分にとっての「見たくない現実」に気づき、みんなでその問題を共有すること。その存在を認め合うこと。すぐに情報化して手放さないこと。要点はこれに尽きます。そのためには、少なくとも自分の内側に「10年間」を内包することが必要となる。哲学者の湯浅泰雄氏のいう、「内なる自然」と向き合うための時間です。「内なる自然」について、湯浅氏はこう述べています。
西洋の『形而上学』がメタ・フィジカ、すなわち「自然(フィシス)」に関する経験の彼方を目指すものだとすれば、東洋の「形而上学」はさしあたりメタ・プシキカともよぶべきもの、すなわち人間の「魂(プシケー)」の内面に見出される経験の彼方を目指すのである。「魂(プシケー)」は「外なる自然」に対する「内なる自然」とよんでもよいであろう。東洋の形而上学がまず第一に問題にしたのは、「内なる自然」としての、肉体の中に埋もれた人間の「魂」のあり方であった。そしてそれを心身の一体性にもとづいて追求していくのが、東洋の形而上学の出発点だったのである[i]。
ぼくが「リアル」と呼んでいるものを、湯浅氏は「内なる自然」「魂(プシケー)」と言っています。しかしこれらを一足飛びに掴むことは、凡人にはとても難しい。「ヴァーチャル」からいったん離れ、しばらく時計も見ずに歩いていたら、靴が泥だらけになっていた。「リアル」とはその泥のような存在なのかもしれません。歩いていれば泥くらいつくのが当たり前。でも「どこを歩くのか」。少なくとも土の上を歩いていなけりゃ、泥がつくことはありません。まずは自分の足で土の上を歩くこと。そして足裏の泥に気づくこと。それが「リアル」の糸口だと感じています。
[i] 湯浅泰雄『身体論 東洋的心身論と現代』講談社、1990年、100頁。