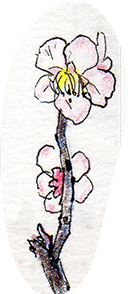しかし、なぜ「本」なのか
信心深くはないのだが、「信じる」という行為の意味や存在意義は身をもって知っている。このような感覚はおかしいのだろうか。
例えば私は「人間の理性では到底計れない世界」があることを信じている。というか「信じる」なんて改まって言うまでもなく、「当たり前じゃん」と思っている。だって人との出会いは全く予測できないし、災害や病気がいつ身に降りかかってくるかなんて、さっぱり分からない。だから銀行とかが言っている、いわゆる「ライフプラン」とかいう壮大なフィクションのなかに生きていく気にはなれないのだ。
さらに言うと、こういう話がスッと通じない人とは話していても面白くないし、だからといって「通じすぎる人」というのも考えもので、どこかで聞いたようなことしか言わなかったりするので、それはそれで興味をなくす。
私が面白いと感じる人は「人間の理性では到底計れない世界」を当たり前に感じつつ、日々理性でもって生きている人。このような人のことを私は「面白い」と感じている。そしてこのような人たちのことを、本来的な意味において「市民」と呼ぶのだと私は勝手に信じている。ベンジャミン・バーバーは、市民社会について以下のように述べる。
自由な国の市民による理想的な組織の中で、「あなたと私」の相互関係を調整する空間が市民社会である。市民社会という言葉が指しているのは自由な社会生活という自律的な領域であり、そこでは政府も民間の市場も絶対的ではない。それは家族、血縁集団、教会、共同体という場で協力し、共通した行為を通じて自分たちのために自ら作り出す領域である。経済的な生産者そして消費者という特定の個人と、主権を持った人民の一員という抽象的な集団との間を媒介する「第三の領域」である(他の二つの領域は国家と市場である)[i]。
さすが、自由な国の理想的な市民は、どこまでも理性に基づいて「主体」にこだわっている。私はバーバーがいうような国家でも市場でもない、「あなたと私」の相互関係を調整する空間を市民社会と呼びたいが、その内実はかなり違ったものになる。
前にも述べたように、社会やコミュニティーの中心には「人間の理性では到底計れない世界」があるべきで、その「世界」を軸に人間集団が形成されるのが好ましいと私は考えている。この「世界」を彼岸と呼び、国家や市場が中心のこちら側の世界を此岸と呼ぶならば、私のいう市民社会は「あっち側とこっち側」を行き来するための橋のような役割をする。そしてこの橋を渡るための通行手形が、本なのである。
[i] ベンジャミン・R・バーバー著、山口晃訳『<私たち>の場所 消費社会から市民社会をとりもどす』4-5頁