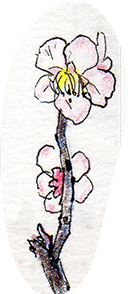わたしがきみで、きみがわたしで
ぼくが勝手に提唱する「土着人類学」は学問ではありません。いうなれば思想です(おおげさですが)。
いわゆる「学問」は主体と客体、つまり「考える自分」と「考えられている対象」を区別します。でも「土着人類学」の場合、主体と客体は常に入れ替わる可能性を秘めているし、他人の考えから影響を受けて自分が新たに生まれ変わることなんて、恥ずかしいことではありません。むしろ推奨すべきことです。じゃあ「土着人類学」とは何なのか。ぼくの2017年のテーマは「土着人類学」について、できるだけ言語化することです。
実は「土着人類学」とは、これから訪れる「答えのない時代」をいかに楽しく送るのかという、極めて実践的な「研究の場」のことを、ぼくが勝手にこう呼んでいるのです。「研究」ではなく「研究の場」といっているのは、ぼくという主体が一人で対象について研究するのではなく、「わたしがきみで、きみがわたしで」研究をしたいという表明です。
「答えのない時代」というのは、「これをすればこういういいことがある」という方程式が存在しない世界です。良い大学に入って就職活動をしてローンで家を買って、というストーリーが「良いもの」として成立しなくなっているのはみなさんご周知のとおりかと思います。だけれど今は、答えがないからいまだにそのストーリーにしがみつかねばならなくなっている。でも答えはない。
こういう時代に勢いづくのは「宗教」です。答えのない時代に、答えを与えてくれるからです。ぼくは人間を超越した「大きいもの」の存在を感じる感覚は不可欠だとは思いますが、「答え、ここにあり」と喧伝する団体に所属はしたくありませんし、そういう人について行くのも性に合いません。では答えはどこにあるのか。だから、答えはありません。肩の力を抜いて、どんな不測の事態にも対応できるようにしておくこと、そのような「状態」になりたいときになれること。「アドリブが利く状態」ともいうことができるし、鈴木大拙師なら「自然にかえれ」と喝破するはず。
この「自然」は「自ずから然る」の義で、仏教者のいう「自然法爾(じねんほうに)である。他からなんらの拘束を受けず、自分本具のものを、そのままにしておく、あるいはそのままで働くの義である。松は松のごとく、竹は竹のごとくで、松と竹と、各自にその法位に住するの義である[i]。
ぼくの言う「アドリブが利く状態」も、鈴木大拙師のいう「自然」に近い。別に会話のなかでなにか気の利いたことを言わねばならない、というのではありません。黙って少し考えるというのも良いと思いますし、よく分からないからもう一回言ってもらえるかな、と聞き返すのもありだと思います。多弁であったり、大声である必要は決してない。問題は「フリーズ」しないこと。へびに睨まれた蛙のように、固まって一歩も動けなくなってしまうとよくない。そうなると「自然」からは遠ざかってしまい、途端に誰かに答えを求めてしまう。
いろいろな本を読むのは、答えを求めるからではありません。知識を蓄え、難敵を論破するためでもありません。たくさんの人の考えや、時代や地域の状況に思いをはせることで、自分の考えの枠、時代の枠、地域の枠に気がつき、「ま、そんなもんかしら」と好きな時に一息つけるようにするためです。
「土着人類学」はどうすればみんなが肩の力を抜いて、「アドリブが利く状態」でいられるのか。どうすれば「自然」に還ることができるのか。そんなことを考え、実験していけるような場でありたいと思っています。
[i] 鈴木大拙著、上田閑照編『新編 東洋的な見方』岩波文庫、1997、219頁。