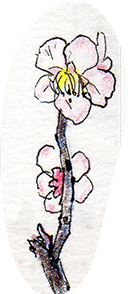「土着人類学」について考える(3)
「土着人類学」の「土着」には、内側と外側の両方のベクトルとが存在する。
外側のベクトルは「土着」本来の意味に近い。広辞苑で「土着」を引くと「先祖代々その土地に住んでいること。また、その土地に住みつくこと」と出てくるが、英語ではindigenousという言葉になるようである。この言葉は「先住の」とか「土着の」といった形容詞で、indigenous people(先住民)のように使用される。つまりindigenousが「時間的に前」という意識とともに使われていることがわかるだろう。
人類の祖先はある時点で二足歩行を始め、故郷のアフリカ大陸を離れて世界中に「住み着く」ことになった。この「グレートジャーニー」くらいの時間スパンで考えてしまうと、後とか先とか、そういう時間的な話がなんだかナンセンスに感じてしまう。もちろん後から来た力の強い者が、もともとそこに住んでいた人びとを追い出して良いという話ではない。そうではないのだけれど、先とか後とかにこだわっていてもなんだかあまり本質的な議論にならないのではないか、と思ってしまう。
もともと、遅れた野蛮な現地民に対して光をもたらすという、近代ヨーロッパの価値観のなかで「土着」は使用され、近代の日本でもその「遅れ」を込めて差別的に「土人」という言葉が使われていた。裏を返せば、いかに「進んでいるか」が重要視された時代、それが「近代」なのであった。その「近代的文脈」は、20世紀も後半に入ると「反転」する。先にいた方、つまり「昔からその土地いた」人びとの逆襲が始まったのである。
しかし私は、いつのまにか「時間的な話」に矮小化されてしまったそのような議論を本質的なものだとは考えていない。先とか後といった時間的尺度と、優劣といった価値的尺度をパラレルに論じることはおかしい。そうではなくて、今までにはない尺度で「土着」を考えることはできないだろうか。つまり「その土地に住む」ということ、それ自体を掘り下げることが私にとって本質的な問題であり、時間的尺度、価値的尺度を省いたそれを「土着」と呼ぼうと思ったのである。
ちなみに現時点では、この「土地に住み着く」つまり「土着」は、農耕を伴った「定住」とイコールではなく、もっと大きな概念として考えている。これもまた、いつかの機会に論じたい。