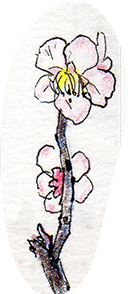「土着人類学」について考える(4)
私は土着人類学の「土着」の英語訳として、indigenousでもnativeでもなく、funkyを充てた。なぜファンキーなのだろう。
辞書でファンキーという言葉を引くと、あまり良い意味がのっていないことに気がつく。もともとは「おじけづいた」とか「臆病な」とか、そういう意味だそうである。しかしファンキーをこのような意味で用いるつもりは毛頭ない。
よく目や耳にする場面としては、やはりブラック・ミュージックと深い関係があるようなのだ。特に60年代のジャズの流行とともに、ファンキーは市民権を得ていったという。このあたりのことは植草甚一さんの著書に詳しい。
北沢夏音さんの著書『Get Back, SUB! あるリトルマガジンの魂』で私は植草甚一さんを知った。1908年、東京日本橋の木綿問屋の一人息子として誕生した植草さんは、主に欧米文学、映画、ジャズの評論家として活躍。特に1970年以降は若者の間でカリスマ的な人気を博した人物だった。しかし残念ながら、79年に亡くなっている。その植草さんは、「ファンキー」についてこのように述べている。
「アメリカ人のジャズ通にむかってファンキーの意味を教えてくれといいますと、みんな口をそろえたように、それは「ブルース的で」bluesy「たましいがあり」soulful「土のにおいがする」earthyと説明づけてくれます[i]」。植草さんは、さらにこの上黒人独特の感じ方や言葉の使い方も踏まえて、ファンキーがジャズ用語として定着していったと説明している。
このように、私が「土着人類学」の訳語として「ファンキー」を使った理由には、「土のにおいがする」アーシーという意味が含まれているからである。ではなぜ、アーシーではなく、ファンキーなのだろう。「土のにおいがする」だけでは、何が足りないのだろう。
それはひとことで言うと、「ゲニウス・ロキ」と関係がある。「ゲニウス・ロキ」つまり地霊が低音を響かせて踊り出っている、そのような動的な意味合いを私はファンキーに込めている。「土のにおい」といった静的で、物静かなイメージではない。土に根付いた、その場所にしか存在し得ない地霊とともに人びとの生活があるような、ソウルフルに近い意味あいを含めたい。
自然と人間が連環のうちにあるような土着な世界が、着々と消えていっているのはさまざまな理由があると思う。産業社会や経済の発展が原因のうちにあげられるだろうし、そもそもこの流れは近代化以降の不可避なものかもしれない。なにはともあれ、「土着」はどんどん消えていく。いつかその世界を取り戻そうと思ったとき、「手がかり」はなにになるだろう。その「手がかり」を考えるところから、土着人類学ははじめていきたいと思っている。
[i] 植草甚一『ファンキー・ジャズの勉強』晶文社、1977年、27-28頁。