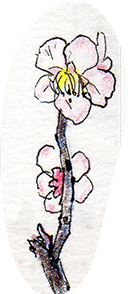「土着人類学」について考える
数年前より「土着人類学Funky Anthropology」を提唱している。この「土着人類学」にはさまざまな問題があるのだが、そのうちのひとつとして、言い出した本人がこの概念についていまいち言語化できていないことがあげられる。「土着とはなにか」「人類学とはなにか」「なぜ土着の英語訳がファンキーなのか」などなど、問題は山積している。
言語化できていないのに提唱するな、と言われるのが普通だし、そんなことは私も重々自覚している。しかし枠組みをつくりながら、そしてその過程について考えつつ進んでいく方が私には合っている。完成品の箱のなかに品物を順番にいれていくよりも、入る品物によって箱の形を変えていくような、そういうインタラクティブな関係こそ健全だと思っているのだ。言い訳おわり。
『芸術人類学』において中沢新一氏は、人類は伝統的に「バイ・ロジック」であったと述べる。本来、「論理的な思考」と論理を飛び越えた「流動的な知性」を併せ持っていた人類は、近代において「合理的な判断」が重要視されすぎた結果、そのバランスを崩してしまった。芸術人類学は「バイ・ロジック」の典型的な形態である芸術と、「未開の民族」に「近代以前」を求め続けた人類学の合わせ技である。それだけでなく、「バイ・ロジック」をも突き抜けたところに存在する「野生の領域」へと踏み込もうとする、「新しいサイエンス」が芸術人類学であるという[i]。
「土着人類学」というネーミング、そしてこの未生成な概念は、中沢氏のこの本から大きく影響を受けている。ただ正直なところ、偉大な思想家である中沢氏の考えを私が十分理解できるわけがなく、ましてや文学的、詩的表現を多用する中沢氏の文章について、果たして「十分な理解」がそもそも可能なのかどうかも怪しい。
中沢氏は本書のなかで芸術人類学を「新しいサイエンス」と定義づけているけれども、私は「土着人類学」をそのように位置づける気も能力もない。いうなれば「芸術人類学」に影響を受けた一人の人間が、自分や身の回りの人との生活のなかでその思想を「研究、実践」していく場が「土着人類学」なのである。
「土着人類学」という場で「研究、実践」すること、それは一言でいうと「自然」に触れながら生きるとはどういうことか、である。この「自然」のなかには木や川、動物、虫といった自然環境や人間の身体、その身体から創りだされるものまで、全てが含まれている。中沢氏のいう「野生」ほど荒々しいものではなく、「折り合いをつけていく」イメージであるから、中沢氏だったら「あ、バイ・ロジックを回復したいんだね」というかもしれない。
つまり「土着人類学」とは、中沢氏が提唱した思想を、ある限られた「自然」に根ざした形で「研究、実践」するとどうなるのか、というアクションそれ自体だともいえる。またその「研究、実践」する人びとが集い、交流するなかで、「土着人類学」が次々に新たな意味を見出していくことも期待している。
[i] 中沢新一『芸術人類学』みすず書房、2006、24-25頁。